本ページはアフィリエイト広告を利用しています
こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
今回は、協同組合が組合員に労働者を派遣するという「特定地域づくり事業協同組合制度」についてご紹介したいと思います。
特定地域づくり事業協同組合制度とは
従来、協同組合の事業として、労働者派遣は出来ないとされていました。
(協同組合が労働者派遣を行うと、基本 派遣先が組合員企業になるので、派遣先が限定された労働者派遣は許可がおりないとされていました。)
しかし、特定地域づくり事業協同組合制度の創設により、「過疎地域又は人口が急減している地域」に限定して、協同組合が組合員を対象とした労働者派遣を行うことが可能となりました。
協同組合が行う労働者派遣の流れは次のとおりです。
- まず、協同組合は派遣労働者を無期雇用します。
- 協同組合は所属している組合員企業に派遣労働者を派遣します。
- 派遣労働者は、組合員企業の指揮命令のもとに仕事を行います。
- 別の日には、派遣労働者は違う組合員企業のもとへ派遣され、そこで仕事を行います。
- 組合員企業は、派遣労働者に来てもらった分だけ利用料を協同組合に支払います。
派遣労働者は、いろいろな組合員のもとへ派遣されるためマルチワーカーと呼ばれます。
派遣労働者にとっては、協同組合に無期雇用されているので給与面で安定している中で、様々な仕事を経験できるメリットがあります。
組合員企業にとっても、通年雇用ではなく、繁忙期など必要なタイミングで派遣職員を利用できるメリットがあります。
そして、この制度の最大のポイントは、派遣労働者の人件費の半額と、組合運営費(事務局担当者の人件費や事務所賃貸料など)の半額が、国と市町村から財政支援(お金が支給)されることです。
★ 派遣職員人件費:1人あたり最大200万円まで支給。
★ 組合運営費:最大300万円まで支給。
財政支援の分だけ、組合員企業からもらう利用料を安く設定したり、組合事務局の運営費が軽減するなど非常に魅力的な制度です。
参照:総務省のHP

特定地域づくり事業を行うには
協同組合が上述の事業を行うには、「特定地域づくり事業協同組合」として認定を受ける必要があります。
前提として、「過疎地域又は人口が急減している地域」に拠点を置く必要があり、新しく協同組合を設立するか既存協同組合の定款を変更して、都道府県の認定を受けなければなりません。
なお、財政支援は市町村と国がそれぞれ一定の割合を負担しながら行うため、拠点とする市町村との理解と協力が必要となります。都道府県への認定も市町村と連絡して行うことになります。
加えて、協同組合が労働者派遣業を行うにあたって、都道府県労働局の許可(この事業に関しては届出という簡易な手続きで良いとされていますが、結局、許可並みの審査を要するようです。)も受ける必要があります。
なんだか簡単ではないような気がします。
まとめ
制度としては令和2年からスタートしており、年々少しずつ新しい特定地域づくり事業協同組合が誕生しています。
総務省HPによると、令和6年2月1日現在で、全国に97件の特定地域づくり事業協同組合があるようです。
財政支援の魅力は大きいですが、人間が関わる事業なので制度設計も複雑で、一般的な協同組合の事業よりも実施が難しいと思います。
しかし、うまく活用できれば地域の活性化に大きな効果が期待できます。
今後も、関連する情報を発信していきたいと思います。
おまけ(お水を買わない。『水道直結型ウォーターサーバー』)
お水を買うのが当たり前の世の中になりました。
多くの方が、ミネラルウォーターなど買ったお水を飲む機会が増えたと思います。
おいしいお水に慣れてくれると、水道水に違和感を感じることがあります。
かと言って、重いお水を定期的に買ってくるのは重労働です。
そこで、楽水(らくみず)の「水道直結型ウォーターサーバー」を試してみてはいかがでしょうか?
水道と直結して水道水を浄水し、おいしいお水をつくるので、「水を買わなくていい」「水を運ばなくていい」「何もしなくていい」の3拍子が揃っています。
ウォーターサーバーは、月々のレンタル料のみでご利用できます。是非、詳細をご覧ください。
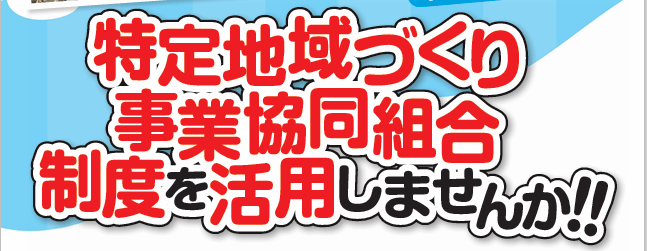


コメント