本ページはアフィリエイト広告を利用しています
こんにちは、黒ひげ コンサルです。
協同組合に関する「お困り事」の解決ヒント情報を発信中です。
この度、ご縁があって「特定地域づくり事業協同組合」の設立に関わることが出来ました。
特定地域づくり事業協同組合制度(以下、特定地域づくり制度)は、
国・市町村からの財政支援受けながら、 過疎地域で協同組合が派遣元となって、
派遣先となる組合員企業のもとへ派遣職員(マルチワーカー)を派遣する仕組みです。
事業協同組合は、派遣職員を無期雇用するので、労働者にとっては安定した雇用環境が確保できます。
組合員企業としては、労働者を通年雇用せずに、繁忙期など必要なタイミングで、派遣労働者を利用することができます。
国・市町村からの財政支援があるので、組合員企業は、割安の利用料で派遣労働者を利用でます。
特定地域づくり制度の詳細については、過去ブログ「協同組合で労働者派遣」や、 下の総務省HPをご覧になってください。
参照:総務省のHP

人口減少で人手不足が深刻な過疎地域にとっては、ものすごく魅力的な制度で、全国的に注目されていますが、いざやろうとするとかなり複雑な仕組みでした。
今回は、私が経験したことから皆様のお役に立ちそうな情報を発信したいと思います。
複数の行政機関が入り混じる仕組み
特定地域づくり制度の最大の魅力は、
派遣労働者(マルチワーカー)人件費の半額補助(1人あたり上限200万円/年)と、
事務局運営費(事務局職員人件費や管理費)の半額補助(上限300万円/年間)です。
この適用を受けるためには、主に次の手続きが必要となります。
- 1 事業協同組合の設立申請(市町村)
- 2 特定地域づくり事業交付金の内示申請(総務省)
- 3 特定地域づくり事業協同組合の認定申請(都道府県庁)
- 4 特定地域づくり事業交付金の本申請(総務省)
- 5 都道府県労働局への労働者派遣業の届出(都道府県労働局)
この4つの手続きをほぼ同時進行で進めていく必要があります。
ある手続きが終わっていないと、次の手続きに進めないなど、各行政機関の手続きが複雑に入り混じっており、窓口となる行政機関との事前打合せや調整が必須となります。
作業量が膨大となるため、まずは設立準備事務局として、各種手続きの中心となる担当者の確保が必要です。
どういった経緯で、特定地域づくり制度の着手に至ったかにもよりますが、
市町村が主体となっている場合は市町村担当者、
地域の企業が中心になっている場合は商工会などの支援機関や農協・漁協といった地場団体の担当者が、 準備事務局の担当者になることが多いようです。
手続きが専門的になるため、一般企業よりも、行政機関や支援機関・業界団体などの担当者の方が向いているのだと思います。
準備事務局担当者は、組合設立を検討している企業の取りまとめや連絡・調整、市町村・総務省・都道府県庁・労働局との事前相談や申請手続きなど、関係者や関係機関と連携しながら作業を進める必要がリ、非常に重要な役割(キーマン)となります。
この準備事務局担当者を確保できるかが、最初のハードルとなります。
担当者を確保できましたら、具体的な手続きの開始となります。
本投稿では、上記枠内1~5のうち1の「事業協同組合の設立申請(市町村)」について説明します。
事業協同組合の設立申請(市町村)について
事業協同組合を設立するには、複数の中小企業が集まり、
集まった中小企業で、事業協同組合の定款や事業計画を作成し、管轄の市町村へ設立申請を行います。市町村から認可をもらえると事業協同組合の設立となります。
ざっくり説明すると、こんな感じですが、実際の手続きはなかなか大変です。
具体的には次の手順となります。
- 1 中小企業を4社以上集める。
- 2 設立同意者を募集する。
- 3 創立総会・理事会を開催する。
- 4 組合設立認可申請を行う。
- 5 法務局に登記する。
それぞれ見ていきたいと思います。
中小企業を4社以上集める
事業協同組合を設立は、中小企業(法人又は個人事業主)が4社以上集まることが要件になっています。
その上で、集まった中小企業の中から発起人を4人以上選出します。
集まった企業が4社であれば、全員が発起人となります。 なお、発起人の権利主体は、法人であれば代表取締役、個人事業主であれば代表者個人となります。
発起人は、組合設立の主体となるメンバーで、発起人が中心となり事業協同組合の定款や事業計画(案)を作成していきます。
実際は、前述した準備事務局担当者が定款、事業計画など必要書類の原案を作成し、発起人会などを開催して発起人に確認してもらう流れになります。
特定地域づくり事業協同組合の設立では、各種手続きで入り混じる複数の行政機関の中でも、特に市町村との連携が重要になります。
財政支援を行うにあたり、市町村では議会での予算承認を得る必要があります。
市町村側とのスケジュール調整や事務処理のすり合わせが重要になりますが、
それ以前に、
そもそも市町村として、特定地域づくり事業協同組合の設立に賛同しているのかなど、
発起人は組合設立の構想段階で、早めに市町村へ相談した方がいいです。
設立同意者を募集する
発起人は、事業協同組合の設立に賛同する企業を募集します。
賛同する企業は、設立同意者と呼ばれ、これから設立する事業協同組合に出資を行います。
出資は、最低1口以上必要で、1口の金額をいくらにするかは、これから作る事業協同組合の定款で定めます。
設立同意者から集めた出資金の総額が、事業協同組合の設立時点での運転資金となります。(株式会社の資本金と同じような考え方)
事業協同組合が設立した暁には、設立同意者は組合員となり組合事業を利用します。
特定地域づくり事業協同組合の場合は、 国・市町村の財政支援が行われるので、
公平性を期すために、広く市町村内の企業に対して、事業協同組合の設立を周知し、賛同するかしないか判断する機会を与えるべきだと思います。
市町村のHPや広報、商工会・商工会議所や地域の団体等を通じた広い周知活動が望ましいでしょう。
創立総会・理事会を開催する
発起人は、設立しようとする事業協同組合について、次の様な必要事項の原案を作成します。
- 1 定款
- 2 1年目と2年目の事業計画
- 3 1年目と2年目の収支予算や、組合員が負担する賦課金
- 4 設立に係る創立費の金額
- 5 役員の報酬額(無報酬もあり)
- 6 借入金残高の最高限度額
- 7 取引先銀行
これらの内容が固まったら、発起人は創立総会の案内を設立同意者に通知します。 創立総会の案内通知は、創立総会開催日の14日以上前に行わなければなりません。
創立総会は、設立同意者の半数以上が出席すれば成立となります。
上記の1~7について審議し、それぞれの議案ごとに、出席者の3分の2以上の賛成をもらえれば可決となります。
また、創立総会では1~7の議案審議に加え、 事業協同組合設立後の役員(理事・監事)を選出します。
理事は最低3人以上、監事は最低1人以上で、事業協同組合の定款で人数を定めます。
選挙方法は、無記名による投票を原則とし、出席者全員の同意があれば指名推選という少し簡易な方法で行うことができます。
・無記名投票 → 誰が誰に投票したかわからにようにして票を入れる。
・指名推選 → 選考委員に役員候補者を選出してもらう。
創立総会の終了後、選出された理事が集まり理事会を開催します。(組合設立途中の理事会)
定款の定めによりますが、理事会は理事の過半数が出席すると成立し、出席理事の過半数の賛成をもらえば可決となります。
この理事会では、「組合設立後の代表理事」と「組合事務所の所在地」を決定します。
設立認可申請を行う
発起人は、創立総会とその後の理事会が終了したら、創立総会議事録と理事会議事録を作成し、事業協同組合の設立認可申請の準備をします。
各市町村によって、申請様式に若干の違いがあるようですが、
主に、次の書類を添えて、管轄市町村に事業協同組合の設立認可申請を行います。
- 1 定款
- 2 事業計画書
- 3 役員の名簿
- 4 設立趣意書
- 5 設立同意者が組合員となれる者であることを誓約した書面
- 6 設立同意者の名簿及び出資口数の内訳
- 7 収支予算
- 8 創立総会と理事会の議事録
- 9 その他、必要な書類
設立認可申請書を受理した市町村では、書類の内容を精査し、問題がなければ認可がなされます。
法務局へ登記する
市町村から事業協同組合の設立認可を得ることができたら、発起人の役目は終わり、発起人から理事へ事務を引き継ぎます。
以降、事業協同組合の運営は理事が執行していくこととなります。
理事は、最初の仕事として、設立同意者に対して出資金の請求を行います。
全ての出資金を受領したら、管轄の法務局へ、事業協同組合の設立を登記申請します。
法務局には、主に書類を添えて登記申請を行います。
- 1 設立登記申請書
- 2 事業協同組合の設立認可書
- 3 設立同意書
- 4 出資の払込領収書
- 5 創立総会と理事会の議事録
- 6 代表理事の個人実印の印鑑証明書
- 7 その他、必要な書類
登記が完了したら、無事、事業協同組合の設立となります。
まとめ
事業協同組合の設立は、多くの手続きを必要とする大変な作業です。
実際、発起人や準備事務局担当者だけの力では、相当難しい作業だと思います。
そこで、事業協同組合の専門支援機関として、中小企業団体中央会という組織があります。
中小企業団体中央会は各都道府県に1つ設置されており、公的支援機関として事業協同組合の設立指導から運営支援を行っています。
ご参考:都道府県中小企業団体中央会
中小企業団体中央会では、組合設立の手順説明やアドバイス、各種必要書類のフォーマットの提供、関係行政庁との調整など、事業協同組合の設立をサポートしてくれます。
公的支援機関なので、基本無料での相談対応が可能で、ほとんどの事業協同組合が中小企業団体中央会のサポートを受けて設立しています。
今回、私が関与した特定地域づくり事業協同組合の設立でも、中小企業団体中央会のサポートを受けています。
だいぶ長文になってしまったので、続きのステップについては次回の投稿で、説明させていただきます。
おまけ(『時間』と『お金』を節約しながら『健康』な食生活へ)
少し前まで、昼食を食べに行くと500円ポッキリのワンコインランチを良く目にしました。
物価が上がり、今ではちょっとした定食で1,000円近くかかってしまいます。
また、外に食べに行くと自分の好きなモノばかり選んで栄養が偏りがちです。
かと言って、自分でお弁当を作るのは大変な作業です。
そこで、ワタミの宅食を試してみてはいかがでしょうか?
健康面が配慮された冷凍総菜が宅配されるので、レンジで温めるだけで食べられます。
1食あたり500円くらいなので、時間もお金も節約して、健康な食生活を実現できます。
初回は、お得な『お試し割』もあるので、是非ご利用ください。
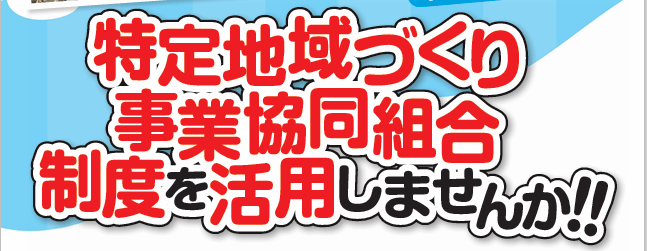


コメント